映画はまさに、家族の「温もり」
瀧川さんにとって、映画との出会いについて教えてください。
映画との出会いは小学生の時です。祖父が亡くなり、迎えた正月が喪中で初詣に行けず、家族全員で3日間とも映画館に行ったんです。その時、映画の作品ではなく、家族が一緒になって楽しめる映画そのものに魅了されました。父はいつも忙しい人だったので、一緒に遊んだ経験も少なく、映画に家族を結びつける「温もり」を感じたのです。それ以降、両親から「どこに連れて行って欲しい?」と聞かれる度に、迷わずに「映画」と答えたものです。
時は過ぎ、学生時代は野球に打ち込み、プロ野球選手を夢見ました。しかし、大学卒業前に怪我をして夢を断念。関東での大学生活はまさに挫折そのものでした。しかし、そんな時も支えとなったのが映画だったのです。
大学を中退し、地元の大阪に戻ってきた僕に家族は「映画が好きなら、映画の国に行って、映画ビジネスのリアルを学んでこい。」とロサンゼルスへの留学を勧めてくれました。そして19歳の時に渡米。その時に出会った仲間たちと夢を語り合い、いつか「ルーカスやスピルバーグのようなプロデューサーとしても有能な映画監督になりたい」と心に決め、帰国後、立命館大学に新設された映像学部への進学を決めたのが、この道の始まりです。
学生時代から積極的に現場へ参加

「Studio-884」を承継するまでの流れを教えてください。
立命館大学で、僕にとって人生を変える出会いがありました。それが映画学科の教授をされていた録音技師の林 基継(はやし もとつぐ)さんです。「Studio-884」はその基継さんの父、土太郎さんが、大映映画の封鎖後、当時の仲間を集めてつくった独立系プロダクションでした。土太郎さんと言えば、映画業界で名をはせた超有名な録音技師でしたから、プロダクションを設立後も数多くのの映画作品に携わられました。そして、2代目の林基継さんになってから、若手育成に力を入れ始め、立命館大学に教えに来られていたのです。
この基継さんのお陰で、僕は山田 洋次 監督や三池 崇史監督などそうそうたる映画監督の制作現場に参加させていただきました。僕が大学を卒業して、プロデューサーや監督として仕事を受託する際にも、基継さんのご好意で「Studio-884」を使わせていただき、また東京でのプロダクション業務においては事務所を作っていただき、支えていただきました。そして、2015年7月に林 土太郎さんがお亡くなりになり、その一ヶ月後になんと基継さんも亡くなってしまいました。その後釜として白羽の矢が立ったのが僕だったのです。悩みましたが、僕が継承することで今まで出会った方々の縁を断ち切ることなく、つながり続けることができると、先輩方にもサポートいただき、代表となり「Studio-884」を受け継ぐことを決めました。
さまざまな作品づくりが今に生きている
いろんな縁が結びついて、今に至るのですね。今、会社を運営する上で大切にされていることは何でしょうか?
大学4年生の時に三池崇史監督のもとで初めて助監督を担当したのですが、当時は映画、CM、ミュージックビデオ、それぞれの制作者が他のジャンルを卑下しているように思え、自分はそうではなく、すべてをこなせる制作者になりたいと考えていました。そして、三池監督のもとで修行した後、映画・CM・ミュージックビデオ・企業VP・観光ビデオなどのさまざまな映像制作に挑戦しました。この経験が大きなターニングポイントになったと思います。今でも、映画会社でありながらあらゆる映像制作を受託していますし、それだけに収まらずラジオ番組で自分がパーソナリティーとなり、さまざまなジャンルのゲストを呼んだりできるのも、今までの経験のおかげだと思っています。
現在の事業内容で特徴的なものを教えてください。
映像制作の中でも特に力を入れて進めているのが、地域創生に関わる映画制作です。日本三大銘醸地の1つとして知られる広島県東広島市・西条を舞台にした映画『恋のしずく』もその1つです。街おこし映画というのは全国各地でよくありますが、その多くが将来的な収益にひも付いていないんです。僕はそうではなく、映画を見ていただいた先に観光客となって街を訪問して宿泊していただく。ご飯も食べて、またリピーターになって、気に入れば移住してもらう。観光消費額が上がると税収も上がるし、移住者が増えて子供が増えると教育機関や医療機関が増え、街が豊かになっていく。つまり、「映画をきっかけに街づくりをしよう」ということなんです。もちろん、僕ら制作者にとっても利益を生まないと意味がないですし、あらゆる具体的なビジョンに基づき、映画づくりを行なっています。
地方創生ムービーづくりにおいて一番大変なことは資金集めですか?
いいえ。もちろん資金集めも大変ですが、何よりも最初の仲間づくりが大変なんです。何のゆかりもない僕らがその土地で映画を作るためには地域に信頼を得ないといけません。そのためには先ほど話したようなしっかりとしたビジネスモデルと、リクープ※1の実現力がないといけません。有名芸能人が出演するから大丈夫とか、面白い台本だから売れるとか、そういうあいまいさではダメなんです。僕らは映画だけではなく、その先にあるインフラや宿泊、飲食など間接的な経済効果までを想定して提案します。まずは国や県、市町村から信頼を得て後援いただき、地元企業からスポンサーを募り、資金集めを進めていきます。最初の仲間集めがうまくいくと資金集めもスムーズに展開できるようになるのです。
※1 損失などを取り戻すことや費用(資金)を回収すること日本と世界をつなぎ、相乗効果で地方創生を目指す

ラジオ番組制作も行う社内の専用スタジオ
将来的なビジョンについて教えてください。
今、日本の地方と海外の地方とつなぐ映画の制作を進めています。それは我々の活動を知った海外の方からコラボをしたいという話をいただいたことがきっかけでした。場所は人口約5600人の小さな街、イタリア、トスカーナ地方のモンタルチーノ。モンタルチーノはワインの街として知られていますが、生産量が少なく、ほとんどが国内消費で終わっています。しかし、モンタルチーノには、世界の注目すべき5人のワイン生産者の一人にあげられているコルデラさんという世界最高峰ランクの称号を持っている女性生産者がいて、そのワインの質はとても素晴らしいものです。最近、コルデラさんの農園に事務所を構えることになりました。それは現在、大阪で進めている「奥河内ムービー・プロジェクト」において、河内長野市を中心とした人口減少が進む地域とモンタルチーノとコラボした「グロカールフィルム※2」の制作を進めているからです。この作品が国際交流の起点となって交換留学生など文化が混じり合うことで、それぞれの地域の成長につながればいいし、この映画をきっかけにビジネス展開ができると思っています。このようなグローカルフィルムを新事業として、今後展開していきたいと思っています。
※2 グローバル(global)な視点で、ローカル( local)の発展を目指す映画それでは最後に、若いクリエイターに一言、お願いします。
僕が三池崇史監督の作品に参加していた頃、三池監督から「今回、お前って意味あったか?」とよく言われたんです。そして、ある日、「自分がここをやったから映画が成立したと自信を持てるくらいの爪あとを残せ。それで失敗したら俺があやまってやる。」と、そうそうたるキャストと大勢のエキストラが入り乱れるシーンを仕切らせていただきました。俳優陣からも「オレらにビビらず、作品作りに力を注げ!」と喝をいただいて、震えながらやったことを覚えています。それが今でも心の中にあって、大切にしていることです。つまり枠組みを作らずに、自分なりの爪あとをしっかり残して、最後までやりきる、作品作りにはそういう覚悟と思いが大切なんじゃないかと思います。
取材日:2018年11月21日 ライター:大垣 知哉
有限会社スタジオ−884
- 代表者名:代表取締役 瀧川元気
- 設立年月:1995年
- 資本金:300万円
- 事業内容:映画・テレビドラマの企画、制作 CM PV VP のプロダクション業務
- 所在地:
- 京都本社 〒616-8184 京都府京都市右京区太秦中筋町20-1 ダイヤビル3F
- TEL/FAX:075-864-1553
- 東京事務所 〒151-0071 東京都渋谷区本町3-27-10
- TEL/FAX:075-864-1553
- 滋賀事務所 〒525-0028 滋賀県草津市上笠2-15-10
- URL:http:// studio-884.com







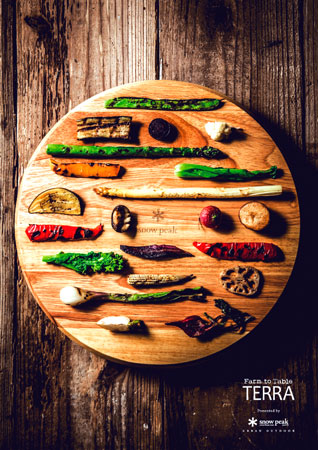







 古今東西のボタンが上品に、しかし圧倒されるほどの種類が並べられていました。ついこちらも緊張してしまいます。
古今東西のボタンが上品に、しかし圧倒されるほどの種類が並べられていました。ついこちらも緊張してしまいます。


















